Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category
6月の心理学コラム:『緑の季節について』(担当:森 康浩)
2021/6/21 >> 役に立つ!!心理学コラム
新緑の季節となりました。街のあちこちで緑が生い茂りとても気持ちがいい季節だと思います。特に定禅寺通りのケヤキ並木は四季折々の顔を見せますが、きれいな景観でとても好きな場所です。車で通る度に、歩いて散歩したいなといつも思います。
このような植物がある景観とリラックスには関係があることが、心理学的にも議論されているのです。
人の特徴として、勉強や仕事をしているときは意識的に対象に注意を向けて、そのことについて取り組むということをします。意識的に注意を向けているので時間が経過することで疲労もたまります。人には他の注意を向けるやり方があって、何気なく無意識的に何かをみるというものもあります。このように自然と向けられる自動的な注意をするときに回復をしようとします。自動的に向けられる注意を引くものの特徴として、魅力的なもの、広さを感じられるものがあります。自然や植物がある景観はこの特徴に合致するので、意識的に注意を向けているときに、ふと自然に注意がいくことでそれまでに感じていた疲労が回復するということになるのです。また、外科的手術をした後に病室から樹木のある景色が見える患者さんの方が、入院日数少なく、鎮痛剤の量も少ないということもわかっています。自然の景色を見るということはとても、いい効果があるので、皆さんも取り入れてみてください。私の研究室からも、中央芝生広場が見え、緑の季節を堪能しています。

5月の心理学コラム:映画の話し『ミッドナイトスワン』(担当:大橋智樹)
2021/5/26 >> 役に立つ!!心理学コラム
今回は、2020年の第44回日本アカデミー賞において最優秀作品賞と最優秀主演男優賞をW受賞した映画『ミッドナイトスワン』を紹介します。この映画は新宿で生きるトランスジェンダー女性(生物学的な性は男性だが自認する性は女性)と親からの虐待を受けていた親戚の女子中学生との同居生活を描く物語です。どちらも自分の居場所、生きる意味を見つけられず、社会の中に居場所がない共通点からか、お互いに通じ合うものを感じながら、徐々に心が通い合っていくが、、、この先は実際に映画を観てください。
この映画の主題はトランスジェンダーや虐待といった社会問題ですが、しかし、誰もが生きていく中で直面するであろう“生きにくさ”に重ねることができると思います。苦しみながら、もがきながら、なんとか前に進もうとし、しかし模索が結果として見つけたものを奪われたり、そんな経験があるのではないでしょうか。理解されずにもがいている人はたくさんいるのです。
この映画はそのような経験に希望の光を与えるものではありません。しかし、現実はハリウッド映画のようにバラ色のエンディングにつながるわけではない。でもそれでも生きねばならないし、その模索は続くのです。
主演の草彅剛と、女子中学生役の新人服部樹咲の演技が素晴らしい。スクリーンから伝わってくる登場人物の放つ空気に圧倒されたり、心を溶かされたり、一緒に胸が苦しくなったりします。ぜひ観てみてください。
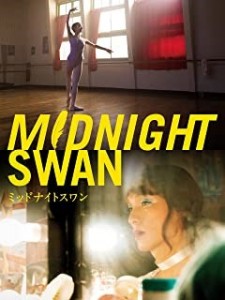
4月の心理学コラム:世界的アイドル✖️ユング心理学(担当:千葉)
2021/4/12 >> 役に立つ!!心理学コラム
こんにちは。4月から本学科の教員として着任しました千葉陽子です。どうぞよろしくお願いします。今回は自己紹介を兼ねて心理学のお話をしようと思います。仙台生まれ仙台育ちで、物心ついた時から競技をしていました。競技に自身の全てをかけて専心する中で、高い緊張場面やプレッシャー下では、「自分を隠せない」ことにある時気づきました。メンタルが弱いとか強いとかの一括りにしてしまえばそれまでですが、自分の性格や心理的課題がそういった場面で露呈するのです。「究極に追い込まれたときにその人の本質が分かる」とはよくいったものです。いろいろ思うことがあり(これについて詳しく語り始めると日が暮れそうですので…)、この世界に足を踏み入れました。大学院では「スポーツ臨床心理学」の第一人者である先生の研究室に所属し、ユング心理学を拠って立つ理論としたアスリートの心の深いところについて学びました。
私は最近知ったのですが、2年ほど前にこの「ユング」があるジャンルで話題になりました。韓国の世界的人気アイドルBTS(防弾少年団)が、「ユング心の地図*」という本をコンセプトにしたアルバムをリリースしたのです。韓国では大きな注目を集め、本書はベストセラーランキング入りとなったようです。アルバムリリースに伴い、メンバーもユングについて学んだと聞きます。日本では絶版となっていましたが、これを機に復刊しました。アルバムの中には「シャドウ」や「ペルソナ」といったユングと関係の深い概念が散りばめられています。トップに上り詰めてスポットライトを浴びれば浴びるほど、その影は深くなっていく。そんなことをアスリートと重ねながら思い耽りました。アイドルはその時代を映す鏡といえるかと思います。その時代に生きる人たちの心を惹きつける彼らは、きっと時代の何かを象徴していると考えられます。私はARMY(BTSファンのことをこう呼ぶそうです)ではありませんが、世界的アイドルグループが本書(心の深層)をコンセプトにアルバムを作成したことに小さな感動を覚え、意味を感じずにはいられませんでした。興味を持たれた方は、PVなどをみるだけでもユングの一部を垣間見ることができますので、是非。
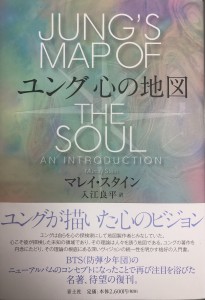
*マレイ・スタイン 入江良平(訳)(2019). ユング 心の地図 新装版 青土社
3月の心理学コラム:つらい経験からの成長(担当:木野和代)
2021/3/9 >> 役に立つ!!心理学コラム
東日本大震災から10年になります。トラウマなどつらい思いを抱えている方もいらっしゃるでしょう。一方で,この経験から学び・成長を感じている方もいらっしゃるかと思います。関連する心理学用語として,それぞれPTSD,PTGがあります(※)。
日本国内の論文検索サイト(Cinii Articles)で,2011年以降の論文を検索してみると,「震災」「PTSD」でヒットしたのは133件でした。「震災」「PTG」では12件でした。11倍の違いです。震災後のPTGの研究はまだまだこれからなのかもしれません。
さて,今月卒業を迎える4年生は,思いもかけぬコロナ禍で大変な思いをしたことでしょう。思い通りにならないことも多く,涙をこらえ切れなかったことが何度かあったでしょう。しかし,この1年を教員目線で振り返ると,4年生の皆さんの成長ぶりがめざましかった様な気がしています。ゼミレポートをみても,学生生活の最後の1年間をやり遂げてできるようになったことが,例年になく多く挙げられていました。それは私の目にもわかる大きな変化でした。なかなか顔を合わせないために,変化に気づくことができたということかもしれませんが,いずれにしても皆さんのこうした成長をうれしく思います。苦難に立ち向かう中で,持っている力をますます発揮するチャンスを得たのかもしれません。自らの力で達成したことを,誇りに思ってください。そして今後に大いに活かしていってください。
これからの新しい生活が,皆さんにとって幸せなものとなりますように。
※「PTSD」(Posttraumatic Stress Disorder)は心的外傷後ストレス障害,「PTG」(Posttraumatic Growth)は外傷後成長と訳されています。関心を持った方はさらに調べてみてください。コロナ禍の学生のPTGについては,ゼミ生が卒業研究で取り組みました。こちらからご覧下さい。
2月の心理学コラム(担当:佐々木隆之)
2021/2/26 >> 役に立つ!!心理学コラム
音楽の聴き方 その2
前回(昨年9月)のコラムでは,初めて聞く音楽と繰り返し聞く音楽で,認知処理に大きな違いがあることを書きました.今回はその続きとして,知っている曲を,ライブなどで生演奏の形で聞くときの聴き方を紹介します.そこでは,また違うプロセスが働いています.人間は機械ではないので,元の音源とまったく同じように演奏することはできません.リズムに微妙な違いが生じたり,表現の仕方が変化したりします.また,それを意図的に行うこともあります.ライブの楽しみの一つは,その日の演奏がいつもとどのように違うかを期待するところにあります.
同じような違いは,映画と舞台の間にもあります.映画は期待通りに進行しますが,舞台演劇は日々いろいろな違いが生じています.どちらにも魅力がありますが,楽しみ方には認知処理という点でも相違があるのです.心理学では,そのようなことも研究のテーマとなります.
今年度は,新型コロナに大きく振り回された1年でしたが,もうすぐ終了,卒業式が近づいてきました.いろいろな制限の中で努力を重ね,卒業論文を仕上げた4年生には心から賞賛の拍手を送りたいと思います.それぞれの進路での活躍を祈ります.
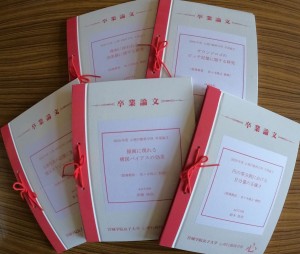
4年生の力作 卒業論文



