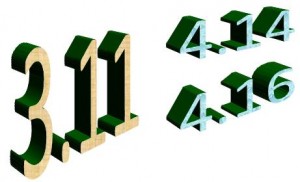Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category
8月の心理学コラム「カタカナ表記の話 その2」(担当:佐々木隆之)
2017/8/26 >> 役に立つ!!心理学コラム
カタカナ表記の話 その2
前回(2017年2月)に日本の芸能人のカタカナ表記について書きましたが、今回はその続き,子音の話です.
ジャッキー・チェンとアグネス・チャンは,どちらも名字がChanだということは前に書きましたが,チャンといえばチャン・グンソクを忘れてはいけません.チャン・グンソクをアルファベットで表記すると,Jang Keun-Sukです.どうしてJangがチャンになるかというと,子音のカテゴリ境界が言語によって違っていることによるものです.日本語の「チャ」と「ジャ」の境界とハングル(朝鮮語)の「チャ」と「ジャ」の境界はずれていて,ハングルの「ジャ」のうちの一部は日本語の「チャ」に聞こえます.グンソクの「グ」と「ク」にも同様の子音のカテゴリ境界のずれが存在します.ペ・ヨンジュン(Bae Yong-Joon)の「ペ」と「ベ」の間も同様です.「ペ」と「ベ」の境界は,英語とタイ語の間で最も大きな違いがあり,スペイン語ではその中間に境界があるという研究報告があります.
日本語の中でも,中田を「なかだ」と読ませるか「なかた」と読ませるかという違いがあります.濁音となる「なかだ」は東日本に多く,清音の「なかた」は西日本に多いそうです.西日本で朝鮮語や中国語の影響が大きかったことが影響している可能性があります.
大学ももうすぐ夏休みが終わり,後期が始まります.10月には大学祭が開催されますが,学科でも例年に増して面白い企画を考えています.ぜひご来場ください.写真は,今年度の大学祭の実行委員です.

大学祭実行委員です.
7月の心理学コラム「ポップコーン作りの話」(担当:工藤敏巳)
2017/7/30 >> 役に立つ!!心理学コラム
先日、卒論の中間発表会がありました。7月8日です。先生方の鋭い指摘に学生たちはタジタジでしたね。いい経験です.発表会の最後に教員が講評を述べる時間が設けられていて、私、結構場違いなことを言ってしまったようです。バームクーヘン作りの話をしてしまったのです。作り方、ご存知ですか?
生地をローラーに垂らして焼き上げていく工程を何度も繰り返すことで,何層にも重なった美味しいバームクーヘンが焼きあがるのです.
この映像をYouTubeで見ていた時,学生指導も結局これと同じではないかと.
教授すべき内容を完璧に伝えても100%吸収してくれるわけでもなく,吸収しきれなかった部分は,吸収できるまで何度も同じことを言い続ける.そして,学生は成長していく.4年生には「先生らしいわ」と慰めの言葉をいただきました.
そんな話を2年生に話したところ,ある学生が「ポップコーン作りも面白いですよ」と言うのです.フライパンを熱してもすぐにパンパン弾けるわけでもなく,ある一定の温度に達した時,フライパン中のコーンがパンパン弾ける.「努力」と「結果」もそれと同じではないかと.努力してもすぐに結果が出るわけでもなく,ある一定の臨界点に達した時,ちょうど水が0度で凍るときと同じように,いきなり成果として表れると言うのです.確かに,成果を残せない人間はすぐに成果が出ないからと言って投げ出してしまう.成果を上げる人間はしつこく努力を積み重ねる.
さらに学生はこう続けます.「先生,弾けないコーンもありますよね?」確かに弾けないコーンもありますね.花の種に水や肥料を同じように与えても,綺麗な花を咲かせる種もあるし,花をつけない種もあります.それと同じように,コーンにも「自主性」,「自発性」と言う力がないと成果を上げられないのかもしれません.
今回は科学と言うよりコーチングの話でした.
6月の心理学コラム「映画の話し『スティング』」(担当:大橋智樹)
2017/6/30 >> 役に立つ!!心理学コラム
私は講演などで,「心を読むことを専門としているのは,心理学者というよりはむしろ手品師か詐欺師だ」とお話ししています。手品師は観客をだませばだますほど拍手喝采を受けるという,なかなか珍しい職業です。詐欺師を褒めるわけにはいきませんが,映画ならば許されるでしょう。今回ご紹介する映画は詐欺映画の最高傑作『スティング』です。
1973年公開のハリウッド映画で,ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードという当代の名優が共演したことでも有名です。第46回アカデミー賞で作品賞,監督賞,脚本賞,主演男優賞など7分野もの受賞という高い評価を受けました。
舞台は1936年のシカゴ。ギャングへの復讐のために,大規模な詐欺を仕掛けるという痛快なコメディ映画です。この復讐で重要なのは,詐欺に遭ったと気づかれないようにギャングを騙すという点にあります。“騙す”という行為は,まさに相手の心を読まないとできません。しかし,騙されたことに気づかないように騙すのはさらに高度なテクニックが必要です。この映画は見事な脚本でそれを描いています。
しかし騙されるのはギャングだけではありません。実は,私たち観客が一番,騙されるのです。是非ご覧になって騙される痛快さを楽しんで下さい。
(※https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51l9NN4g5yL.jpg)
5月の心理学コラム:ドラマ10『お母さん、娘をやめていいですか?』(担当:木野和代)
2017/5/14 >> 役に立つ!!心理学コラム
ドキッとするタイトルが気になって、つい毎週視聴。2017年1月スタートのNHKドラマである。
脚本家曰く「母と娘の一筋縄ではいかない「ラブストーリー」」。親友のように仲良しで、気の合う母娘。娘にとって母は良き相談相手のように見える。しかし、心の奥では母親からの自立を望んでいることが、母親への唯一の秘密という10円ハゲに表されている。
母親が嫌いなわけではない。むしろ好きだから離れられない。恋人と距離をおくことになっても、母親の元へ戻ってしまう。臨床心理士の信田さよ子氏がその著書『母が重くてたまらない』の中であげた6つの母娘関係のうち「同志としての母親-絆から離脱不能な娘」に重なった。
NHKのドラマということは、社会的関心の高い/関心を持ってもらいたい題材ということだろう。番組HPの掲示板には、放送開始後から数えても1000件を超える書き込み。自分の体験に重ねた内容も多い。「自分だけではなかったことに驚いた」というコメントも。
家族の問題は、家の中だけに閉ざされがちで、子どもが相対化して捉えることが難しいという。信田氏が先の著書で一般向けにわかりやすく問題の親子関係を整理されていた理由もそこにある。その意味で、このドラマの意義は大きいと感じる。
そういえば、最終回のサブタイトルは『人形の家』。娘の自立を意味するメインタイトルとは裏腹に、実は「母親の子離れ」もこのドラマのテーマだったように思う。娘だけではなく、母親も「自分自身の人生」を自らの選択で歩んでいくという部分がもう一つの見所だったのではないだろうか。娘たちだけでなく、母たちにも捧げられたドラマだったのかもしれない。
4月の心理学コラム 「熊本地震と東日本大震災」 (担当:友野隆成)
2017/4/20 >> 役に立つ!!心理学コラム
突然ですが,皆さんは熊本地震が何月何日に発生したか,パッと思い出すことはできますでしょうか?正解は,前震が2016年の4月14日,本震が2日後の16日でした。熊本地震の発災から1年が経過し,ここのところテレビや新聞などでも報道されていましたので,思い出すことができた方も少なくないのではないでしょうか。
話は遡ること約半年前,心理行動実践セミナーで私が担当した班のうち,熊本地震と東日本大震災の義援金寄付について比較検討したチームがありました。大学祭でそれぞれの被災地宛の募金箱を設置し,どちらにより多く募金されるかを実験したのですが,その際に2つの地震の発災日を正しく覚えているかどうかを調査しました。その結果,正答率は東日本大震災が94%であったのに対して,熊本地震はわずか8%でした。発生から5年以上経過した東日本大震災のことは覚えられていても,たった半年程度しか経過していない熊本地震のことはほとんど覚えられていなかったことが示されました(因みに,この質問を調査項目に入れるかどうか受講生の皆さんと検討していた際,恥ずかしながら私も答えられませんでした…)。
この実験がなされていた時間帯に実際に寄付された募金額も,宮城県(5,349円)に比べて熊本県(4,308円)の方が少なかったことも示され,単純に発災日が近いかどうかということではなく,物理的・心理的距離の方が義援金寄付に影響を与えている可能性が示唆されました。何とも切ない結果ではありましたが,私個人は却って熊本への想いが強くなりました。できることは限られていますが,やれることをやっていければと思います。