Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category
6月の心理学コラム「心のコントロール」(担当:大橋智樹)
2018/7/3 >> 役に立つ!!心理学コラム
サッカーのW杯,ベスト8をかけた決勝トーナメント1回戦。前半を0点に抑えた日本は,後半開始早々,立て続けに2点を取りました。見ていてとても興奮しました。これまで日本のサッカー界にはMFはいるけれどFWがいないと言われてきました。しかし,原口,乾両選手のゴールは,世界トップ選手と比較しても見劣りしないものでした。特に,乾選手は,セネガル戦でのカーブをかけて右サイドネットに突き刺したゴールに続き,今度は無回転のシュートを叩き込んだもので,日本人にもこんなことができる選手が出てきたのか!ととても驚きました。しかし,日本はこの2点を守り切ることができずに,後半アディショナルタイムが終わる寸前にカウンターから3点目を決められて万事休す。ベスト8には進めずに敗退しました。
敗因はいくつもあると思いますが,私はメンタル面の差が大きかったように感じます。代表戦で2年近く無敗を誇るベルギーは,2点を先行されても負けるとは思わなかったことでしょう。それに対し,勝てるかもしれないと思ってしまった日本代表は,追いつかれたことで気持ちが切れたように見えました。平常心を保ってプレイすることができれば,少なくとも延長戦には持ち込めたでしょう。勝機への意識,残り時間への意識,そういった複雑な「心」が負けを呼び込んだように感じます。同じくロスタイムで失点をした1993年の“ドーハの悲劇”からあまり成長していないように思います。
心のコントロールは心理学の目的の一つです。スポーツだけでなく,さまざまな場面でその必要性は高まりつつあります。そんなニーズに応えられる心理学でありたいと思います。

5月の心理学コラム:映画『ウィンストン・チャーチル』にみる英雄像(担当:木野和代)
2018/5/11 >> 役に立つ!!心理学コラム
GW中、観に行ってみた。昨年のアカデミー賞で辻氏がメイクアップ&ヘアスタイリング賞を受賞したことでも話題になった映画である。
映画の前に予習で、インターネットでチャーチルを調べ、イギリス文学を専門とする夫にもそのイメージを聞いてみた。冷酷な独裁者、偏屈者、戦時中に必要だった人などなど、どうもリーダーとしては歓迎したくない人物像が多かった。
ところが、今回の映画の広告を見てみると、『「嫌われ者」から「伝説のリーダー」となったチャーチルの真実の物語』とあり、日本語の副題には、「ヒトラーから世界を救った男」とある。どうやら、これまでとは違った「英雄」としてのチャーチルが描かれているようだ。
英雄といえば、先日、図書館で小此木啓吾先生の『英雄の心理学』という本を見つけて借りたところだった。様々な日本の英雄を取りあげながら、時代によって、どのように英雄像が変わっていったかを紹介している。例えば徳川家康。1930年生まれの小此木先生の少年時代、家康と言えばタヌキ親父で、英雄と呼ぶには程遠い人物だったそうだ。それが、1983年にNHK大河ドラマでとりあげられた辺りから、変わったとのこと。そこには、低成長時代の保守化心理や第二次世界大戦後の民主化など、日本社会の変化が読み取れると言う。「英雄像」も、その時代や社会を生きる人間によって修正が加えられていく、ということだ。
映画の中のチャーチルは、難局にあっても信念を貫いた英傑であると同時に、悩み、迷う、一人の人間でもあった。歴史を変えるほどの決断を迫られたとき、彼は、単身、地下鉄に乗り込み、市民の声に耳を傾ける。とても印象的なシーンだ。当のイギリス国民にどのように映ったか気になるところだが、遠い日本でこの映画を観て心打たれる私達の「英雄像」も、映し出されていることに間違いはないだろう。
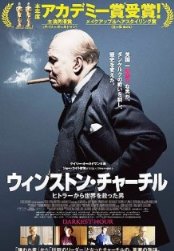
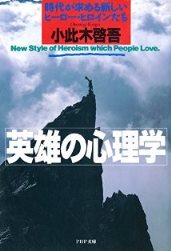
4月の心理学コラム 「偶然の重なりその2」(担当:友野隆成)
2018/4/21 >> 役に立つ!!心理学コラム
前回のコラム「偶然の重なり」で,本文とは直接関係のない熊本城の写真を載せました。今回は,その話について書きたいと思います。
前回のコラムでは,昨年9月20~22日に久留米で開催された日本心理学会に参加してきた旨お話しました。一昨年に熊本地震の義援金募集活動を行ったこともあり,せっかく九州に行くのだから熊本へも訪れておきたいという淡い気持ちがありました。いろいろ調べてみると,久留米から九州新幹線に乗れば20分くらいで行けることがわかり,学会の合間に急遽行ってみることにしました。
熊本へは,十数年前に別の学会で行ったことがありましたが,ほとんど記憶が残っていなかったため,ほぼ初めて訪れるような感覚でした(前に行った時は,まだ九州新幹線は走っていませんでしたし)。熊本の市街地の中心部は,東日本大震災時における仙台市の市街地の中心部がそうであったように,復興がかなり進んでおり,一年半前に大地震が発生したとは思えないほどでした。そう,ある場所を除いては。
そのある場所というのが,前回写真を載せた熊本城です。熊本城の修復が終わるまで,20年ほどかかるという話もあるようで,そこの空間だけが時間の流れから取り残されているような感覚がありました。
仙台に戻った後,心理行動実践セミナーの授業時にこの話を受講生の皆さんにしました。そうしましたところ,漠然と熊本地震の義援金を集めることは決まっていたが具体的に何をやるのかが全然決まっていなかったチームから,「熊本城の復興募金を集める活動にしたい」という申し出がありました。そして,以下の写真のようなピタゴラスイッチ風の募金箱を作成し,募金を集めました。
結果としては,残念ながら期待されたほどの効果はありませんでしたが,少ない額でも熊本城の復興に使ってもらえる募金を集めることができました。私が偶然熊本城に訪れていなかったら,この話もなかったのではないかと思います。以上,偶然が偶然を呼んだ出来事のお話でした。

熊本城の復興募金に使用した募金箱(ピタゴラスイッチ風)
3月の心理学コラム「失う時の人の心理」(担当:森 康浩)
2018/3/15 >> 役に立つ!!心理学コラム
3月は旅立ちの季節ですね。
今年度は4学年受け持ち、私のゼミ生も無事に心理行動科学科を巣立っていきました。
就活と平行させて、卒論にひたむきに向かい素晴らしいものを仕上げてくれました。
よく頑張ってくれたなと思っております。
さて、みなさんは増えることと、減ることどちらに意識が向きますか?
例えば、1万円の臨時収入を得たときの喜びと1万円が入った封筒をどこかで落としてしまった時の悲しみでは、どちらが心理的な影響が大きいでしょうか?
Kahneman & Tversky (1979)によると、人は損失のショックの方が心理的に大きく感じられ、それを回避しようとする傾向があることを示しています。
4年生が卒業してしまい、失ってしまったというショックがありますが、彼女らの将来を考えると必要な損失なのかも知れません。
心理行動科学科で得た学びを用いて、社会という大海原で大活躍してくれれば良いかなと思います。
今回失ってしまったという悲しみが吹き飛んでしまうような、うれしい連絡がたくさん来ることを願っています!!

2月の心理学コラム「別れの音楽の話」(担当:佐々木隆之)
2018/2/7 >> 役に立つ!!心理学コラム
4年生は,学びの集大成としての卒業論文を提出し,卒業式を待つばかりとなりました.ゼミの学生たちもそれぞれに進む道を決め,もうすぐ巣立っていきます.
ところで,別れの音楽といえばだれもが思い出す曲が「蛍の光」です.毎年,年末の紅白歌合戦の最後に合唱される音楽でもありますし,知らない人はいないでしょう.それでは,商業施設の閉館や公共施設の閉店のときに流れる音楽は,と聞くと,これも「蛍の光」だという人がいます.しかし,厳密にいうとこれは間違っています.デパートで閉店間際に流される音楽は,「蛍の光」のアレンジ曲で「別れのワルツ」という名前がついています.下の楽譜を見るとわかるように,「蛍の光」は4拍子で,「別れのワルツ」はワルツというぐらいですから3拍子です.「蛍の光」を歌ってくださいと頼むと,「別れのワルツ」を歌う人が多いのですが,これは普段の生活では3拍子の「別れのワルツ」の方を耳にする機会が多いからだと思われます.
年度末も近づき,1年間のあんなことやこんなこと,いろいろなことが思い出されます.巣立っていくみんなが幸せになるよう祈っています.

「蛍の光」と「別れのワルツ」の楽譜

ゼミの思い出の一コマ


