Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category
11月の心理学コラム:私こそ真のミッキー・ファン?(担当:木野和代)
2018/11/19 >> 役に立つ!!心理学コラム
「ミート・ミッキーに660分待ち」というニュースが、今日(11月19日)のゼミで話題になりました。
1928年11月18日はミッキーがスクリーンデビューを果たした日で、昨日は90歳の誕生日。「記念日をお祝いしたい」と、TDLの「ミッキーの家とミート・ミッキー」にたくさんの人が押し寄せたとのことです。整理券が配られたものの、グループの誰かは並んでいなくてはいけないルール。
11時間待ちと聞いただけで疲れてしまい、そんな行列に並ぶなんて信じられない…と思ってしまうのは私だけではないようで、学生たちも同じように驚いていました。
実際に何時間も待った人たちはさぞかし疲れたことでしょう。ですが、それ以上に、うれしさや満足感で満たされ、ミッキーのことが一層好きになった人も多かったのではないでしょうか。そんな現象を「認知的不協和理論」で説明することができます。
認知的不協和理論とは、二つの矛盾する「認知」を同時に持つと、私たちはしばしば不快な気持になりますが、その不快感を軽減するために、矛盾する認知のどちらか一方を変えてしまったり、片方の認知を弱めてもう一方を強めたり、一方の認知を補強する情報を探したり、矛盾する認知に関する情報を選択的に避けたりするというものです。
何時間も待って、90歳の誕生日にお祝いの気持ちを伝えたことで、ミッキーへの親近感を強め、「それくらい私はミッキーが好きなんだ」「ミッキーも喜んでくれた」「楽しかった」と思いたい、というわけです。
夢の国TDLのお話なのに、夢のない話をしてしまいましたね・・・。ですが、こうしたことは、誰でも日常生活のいろんな場面で出くわしているのではないでしょうか。
さて、ミッキーのおかげで6年前に書いたコラム(2012.11.12upload)で予告していた「続き」が、ようやく書けました(笑)。続きとはどういう意味かは、皆さんで考えてみてください。
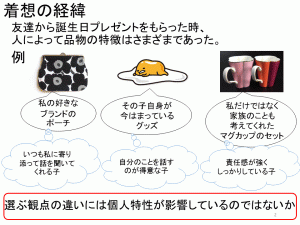
以上、卒業研究で誕生日プレゼントを題材にしている学生たちとの会話からでした。写真は彼女たちの卒業研究中間発表会資料の一部。
10月の心理学コラム:日本心理学会(担当:友野隆成)
2018/10/15 >> 役に立つ!!心理学コラム
9月25~27日の3日間,仙台国際センターで開催された日本心理学会第82回大会(東北大学主催)に参加してきました。今回は,地元仙台での開催ということもあり,3つのシンポジウムに登壇する機会をいただきましたので,1つずつ振り返ってみようと思います。
まずは,26日の午前中に開催された公募シンポジウム「われわれは“曖昧な世界” にいかに向き合うのか?2―“曖昧さへの態度”概念の精緻化をめざして―」です。私の研究テーマである「曖昧さ耐性」について,知り合いの先生方と去年から始めたシンポジウムです。今回は,「対人場面における曖昧さへの非寛容と曖昧さへの態度の比較」というタイトルで,「曖昧さへの態度」よりも「対人場面における曖昧さへの非寛容」の方が,より抑うつの予測に関して有効であるということを発表しました。全体討論の中で,非常に困難ではあるが,曖昧さのなかにある曖昧さをできるだけなくしていくことが重要であるという話になりました。どこまで曖昧さの曖昧さをなくせるか,今後せめぎあいが続くことでしょう。ちなみに,本学科の学生数名が冷やかしに来てくれました。
続いて,26日の午後に開催された公募シンポジウム「研究活動の行動科学―研究の継続要因を探る―」です。このシンポジウムは第26回日本行動科学学会年次大会と共催であり,企画代表者兼大会長として,企画趣旨の説明を行いました。これまで同一テーマで継続してご研究をされている先生方に,いかに研究を継続させてきたかを熱く語っていただきました。今回は3つのグループの先生方から話題提供をしていただきましたが,グループメンバーの緩い人間関係と相補性,そして科研費獲得が研究継続を促進させる要因として機能していることが垣間見られました。
最後は, 27日の最終セッションに開催された日本心理学会企画シンポジウム「災害復興と心理学」です。このシンポジウムは,日本心理学会の研究助成である,「東日本大震災からの復興のための実践活動及び研究」に採択された研究課題について話題提供を行うもので,私は2015年度の助成に採択された,「義援金寄付行動を対象とした持続可能な被災地支援に関する心理学的実践研究」について話題提供を行いました。2015年度および2016年度の実践ゼミで実施した活動をもとに,義援金を効果的に集めるためには,寄付をしていただける可能性のある方々の特性を把握することや,それに即した情報の提示と募金箱の設置など,ちょっとした工夫が有効であることを発表しました。他の先生方の話題提供は,自殺防止のゲートキーパーや自衛隊員に関するものであり,被災地支援にも色々なかたちがあるということを再確認しました。
以上,内容的には全くと言っていいほど関連がなさそうな3つのシンポジウムでしたが,共通する部分としては「継続性」が挙げられるのではないかと思います。今後も,色々と継続して頑張っていきたいと思います。
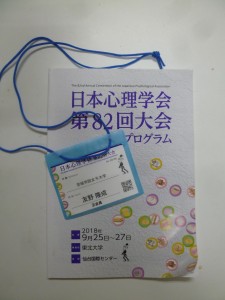
日本心理学会第82回大会の参加章とプログラム
9月の心理学コラム:行動を誘発する”もの” (担当:森康浩)
2018/9/10 >> 役に立つ!!心理学コラム
皆さん。下の写真のような状況に出くわしたとしたら、どのように行動しますか?
これはエスカレーターを降りたすぐ直後に、フロアーの部分に足跡が書かれているというものです。
足跡の向きに従って歩いて行きますか?
エスカレーターを降りる際に足下に注意を向けるので視界に入りやすいですし、足跡を目でたどって、その先にあるものを見て、移動することを決めると思います。
私たちの身の回りには、いろいろな形のものやいろいろな配置のものがあります。
ここまで話してきたものには、アフォーダンスという名前がついています。
アフォーダンスとはGibson(1979)が提唱したものであり、生活環境の中に存在するものの形状や材質といった特徴から行動が誘発されることを指しています。
例えば、取っ手つきのコーヒーカップを持つ際に、多くの人が取っ手を持って飲み物を飲むと思います。誰かが「取っ手を持たなければいけないんだよ」ということを教えてくれたわけではありませんが、そのような行動を人はします。また、小さいときに横断歩道の白い部分から落ちないように渡ったことがあるともいます。これもアフォーダンスです。
皆さんの日常の中にどのくらいアフォーダンスがあるか探して見てください。
8月の心理学コラム:アジア競技大会ダイアリー(担当:工藤敏巳)
2018/9/1 >> 役に立つ!!心理学コラム
毎回、学科のエッセイを書くにあたり、何を書くか悩みます。今回は先月から開催されたアジア競技大会(ソフトテニス競技)に選手団と帯同しているので、その時々で思ったこと、感じたことについて綴ってみたいと思います。
8月24日(出発日)
宮城学院発の夕方のバスに乗車し、仙台駅に向かう。
17時30分発の新幹線で上野駅に向かう。金曜日の夕方からか、普通指定席が取れず、ちょっとリッチな気分でグリーン席。しかし、ここもほぼ満席。
堀江モンさんみたいな方がいるといけないので、いきなり後ろを振り向かず、リクライニングを倒してみる。確かに、いちいち後ろの方に確認してシートを倒す必要もないが、それに腹をたてるのもどうかと思う。
JR上野駅から京成線乗換まで少しだけ歩くので面倒くさい。雨が降っていないといいが。東京駅から成田エクスプレスに乗ろうとしても、総武線の乗り口は遠いので結局は同じだろうか。
大学を卒業してから上野駅には寄る機会がほとんどない。10年くらい前に京成線に乗車した記憶があったが、今とほとんど変わっていない印象だ。
学生時代には、40年も前には、筑波大学の宿舎に帰るにはJR常磐線で荒川沖駅下車したので、東京に行く時には必ず上野駅を経由したので、懐かしい。
日本ソフトテニス連盟が用意してくれたホテルに宿泊し、明日は8時に成田空港に集合です。ここ2、3日、ゲーム解析のコード作りを頑張っていたので眼の疲労がハンパない。明日、遅刻しないといいが。
8月25日
ジャカルタでパレンバン行き便の出発待ち。
成田空港第二ターミナルでは、アジア大会専用カウンターが設けられており、すんなり手続きが完了した。
陸上競技の短距離が始まるらしく、桐生選手に遭遇。報道陣の取材を受けていた。カヌーの選手団も同じ便で、知り合いのカヌーチームのトレーナーに「メダリストも来ているの?」と聞いたら聞こえなかったのか「?」と返答。結局ナマ羽根田選手に会えずに残念でした。競技会場が同じなので、スケジュールをチェックし見に行こうと思う。
7時間の機内で同じ姿勢を取り続けると回復が大変なので、選手たちは時々機内は立って過ごしている。コンディショニングには気を使う。
8月26日
昨晩、0時にホテル到着なのに、朝は6時出発でした。まぁいつものことです。
対戦国の練習を撮影し分析する。午後は会場から市内のスーパーマーケットまでモノレールを使って、買い出し。選手用の日本食の食材を買う。キャベツとかじゃがいもとか。何でもお好み焼きを作るらしい。グリコーゲンローディングです。下痢を起こしたら一大事なので食事には気を遣う。トレーナーが炊事をして、いろいろ献立を考えているようだ。
パレンバンのモノレールは出来たばかりで大勢の一般客で混雑していた。乗車客をプラットホームにあげず、改札口で待たせるシステム。確かに子供達には転落の可能性があるので、いいシステムだと思う。しかし、30分間隔だからなせる技で、山手線ではできない。
夕方、対戦国が練習しなかったので少し時間が出来た。テニスセンターの隣の会場でスポーツクライミングをやっていたので、それを視察した。これが面白い。
8月27日
ホテルで朝食。出発時間を昨日より30分遅らせたので、朝食がとれるようになった。
8月28日
本日は、シングルス。予選からQuarterFinalまで。
帰りのモノレール最終に乗り遅れ、急遽、タクシーでホテルへ。幸い、駅にアジア大会のボランティアの方がいたのでタクシーをよんでもらえたからよかったが、パレンバンでタクシーを見つけるのは至難の技だと思う。だいたいホテルの住所すら知らない。
8月29日
今朝も昨日に続いて5時半出発。シングルスの準決勝、決勝。ジングルスは最大の山場、こういう時は、監督、スタッフ、選手はいつも無口。必要最低限の会話に緊張感が漂う。午後からはミックスダブルス予選が始まる。
8月30日
毎朝、監督スタッフに飲んでもらおうとコーヒーを入れて会場に行く。今日も。
ゆっくりしてもらいたいのと、カフェインを入れて眠気を追い払うためである。しかし、もはやスタッフの疲労はピークに達しているようでカフェインなんかは効かないようだ。
Twitterを見ると、結果や映像がたくさんアップされている。確かに人より早くアップすればアクセス数が増えるのだろう。しかし、そうした情報の即時性よりも情報に付加価値を与えることの方が重要に思える。つまり、情報に関して意見や考えを述べる。その方が読んでいて興味が湧く。
また、情報に偏りがある。日本に関する情報が圧倒的に多く海外情報が少ない。
9月1日
団体戦決勝。男子は惜しくも韓国に負けてしまいましたが、女子が韓国に勝ち、金メダルを獲得しました。しかし、ホッとしている暇はありません。見つかった課題に取り組んで、前進していきたいと思います。
明日は帰国です。ホテルにバスタブがなかったので、帰国したら湯船ゆっくり浸かりたいですね。
7月の心理学コラム:楽器の話 その1 ファゴット(担当:佐々木隆之)
2018/8/2 >> 役に立つ!!心理学コラム
ファゴットは,バスーンとも呼ばれるダブルリードの木管楽器です.私の知り合いのファゴット奏者は,バスーンと呼ぶことを異様に嫌っていました.その理由を聞いた記憶はあるのですが,中身はすっかり忘れてしまいました.
ファゴットの特徴は,なんと言ってもそのとぼけた音色にあります.NHKの子供番組では,かなりの割合でファゴットによるBGMが使われています.また,サザエさんやドラえもんのようなアニメの中でも,独特の雰囲気を作るために効果的に使われています.なぜファゴットの音がとぼけて聞こえるかというと,その理由の一つとして楽器の共鳴が挙げられます.ファゴットは他の楽器に比べて,かなり人間の声に近い共鳴構造を持っていると考えられます.そのため,ファゴットの音を聞くと人間の声を連想し,意味の分からないスキャットのような印象を受けます.人の言葉をしゃべる動物に近い印象で,親近感も生じさせます.クレヨンしんちゃんでもファゴットはBGMに使われていますが,クレヨンしんちゃんの発声がファゴットに近く,とても面白く感じて好きです.
同じ二枚舌の木管楽器であるコールアングレ(イングリッシュホルン)やトランペットにハーマンミュート(ワウワウミュート)をつけた音も同様の印象ですが,ファゴットの方が人間の声の音域に近い分特徴が際立っています.機会があったら注目して聞いてみてください.
去る7月15日(日)に,東北大学でサイエンスデイという催しがあり,2人の学生と一緒に出展しました.6時間の間に,小学生の子どもと親,そして時々大学生が800人近く訪れ,錯視パターンの作成を楽しんでもらいました.休む間もなくずっと対応し続けとなり,大変疲れましたが,皆が楽しんでくれているのを実感でき,充実感も味わいました.3年生の蓮池美沙樹さん,小島南さん,ご苦労様でした.

サイエンスデイ2018 その1

サイエンスデイ2018 その2



