1月の心理学コラム:『あしたの君へ』(担当:木野和代)
2022/1/10 >> 役に立つ!!心理学コラム
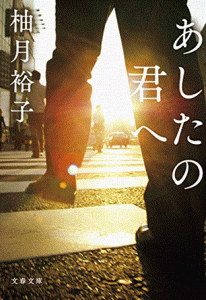 柚月裕子さんによる小説です。実務修習中の家庭裁判所調査官補が主人公の物語で,彼が実際の少年事件,家事事件を担当していく中でのとまどいや葛藤,成長が描かれています。
柚月裕子さんによる小説です。実務修習中の家庭裁判所調査官補が主人公の物語で,彼が実際の少年事件,家事事件を担当していく中でのとまどいや葛藤,成長が描かれています。
家庭裁判所調査官というのは心理学を活かすことができる専門職の一つです。主人公は自分はこの仕事に向いていないといいながらも,担当案件の少年少女や夫婦・子ども,それぞれが生きている現実によりそい,これからのために必要なこと,最適なことは何かを考えます。そんな仕事の様子がとてもリアルに描かれているように感じました。
ちなみに,主人公の修習先の主任調査官の持論は,「家裁調査官の仕事で重要な3つの心得は,常に相談者の立場になって調査すること,常に周りに相談すること,常に健康に留意すること」です。それぞれが大切な理由は,ぜひ小説で確認していただきたいですが,この3つ,私は多くの仕事で重要な心得だと思いました。
実際,11月~12月にかけて卒業研究で4年生のゼミ生達がデータ収集をしていたときも,彼女達には,研究に参加してくれる人の立場で考え,周りに相談し,心身の健康に気をつけることを何度も念押ししていました(笑)。
話はもどって,この小説の巻末には,家庭裁判所調査官の益田浄子さんが解説を寄せていらっしゃいますが,益田さんによれば,身近な人にも家裁調査官の仕事を正しく理解してもらうのが難しいそうです。この小説は,そんなお仕事を理解する資料の一つになるのではないでしょうか。また,心理学を活かした専門職に関心のある方にもお勧めです。本学の大学図書館でも所蔵していますので,是非読んでみてください。
12月の心理行動科学科
2021/12/31 >> 今月の心理行動科学科
朝晩の冷えが厳しくなってきましたね。
12月11日(土)にオープンキャンパスが行われました。
体験コーナーでは鏡映描写やウソ発見器を体験していただきました。
実践研究報告は11月23日にアエルで報告した学生が、先日の経験を活かし、さらにわかりやすく説明をしていました。
森先生による学科紹介・模擬授業では、高校生だけではなく保護者のみなさんも熱心に聞いてくださいました。
12月18日(土)には、大学後援会特別企画が開催され、保護者の方々が、進路相談や学科の懇談会に出席されました。
12月26日(日)には、大学祭企画「ココロミル2021」をSELVAで行いました。
性格診断や錯覚の展示、鏡映描写やストループ効果の体験などを行いました。
12月のリレーエッセイ(千葉ゼミ3年・大場日菜子さん)
2021/12/20 >> 在学生によるリレーエッセイ
こんにちは!3年千葉ゼミ 健康元気に大場日菜子です。
同学年の髪の毛が黒くなる季節が来ましたね。
そんな中、私は今日も変わらず美容師さんに「限りなくブルーで!」とオーダーしました。ブリーチしていないので黒くなるだけですが、自己満ってやつです。
最近の私は学びに飢えています。今期の講義で素敵な言葉をいただきました。
「無学の上に個性は咲かない」です。
机の上で行う勉強だけではなく、日常や外の世界での学びが沢山あります。本学科のモットーと似ていますね。
若いうちに沢山学びを吸収して、経験値が欲しいです!
また、この時期になると就活も始まり自己分析など自分自身を見つめ直す機会が多くなりました。
自身の新たな一面や発見があり面白いです。四年生に向けて出来ることから準備をすすめていきます。
この写真は一人一人がそれぞれの進路を考えつつ、みんなで卒業にむけて助け合う千葉ゼミです!
出逢いに感謝!
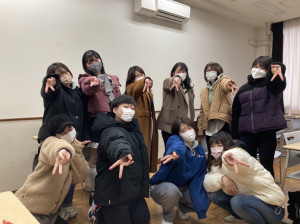
タイトル:我等友情永久不滅
12月の心理学コラム:『嬉しいプレゼントとは?』(担当:森 康浩)
2021/12/10 >> 役に立つ!!心理学コラム
年の瀬が近づいてきて、慌ただしい季節となってきました。12月は師走というように、自分も例に漏れずに日々、頭と体をフル回転させて邁進しております。そんな12月は、いろいろなイベントがあり、人にプレゼントを渡す機会も多いのかもしれません。自分も2児のパパなので、白いひげのはえた赤い服が似合い、トナカイを乗り回すおじさんにならなければならないので、プレゼントとして何をもらったら子ども達が喜ぶのか探りをお入れなければなりません。
今回はプレゼントについて心理学と関わりのあることを書こうと思います。
普段皆さんは、誕生日なりクリスマスなり贈り物をもらうタイミングでどのようなものをもらいますか?嬉しいものもあれば、とても残念だなと思うものもあるかもしれません。プレゼントを選ぶ際に、プレゼントをもらった人が喜ぶものではなく、面白いだろうなと思ってプレゼントを選ぶ場合もあるのではないでしょうか。
プレゼントを贈る際は、相手が欲しいもののリストを作成して、その中から渡すものを選ぶことで、相手が喜ぶプレゼントを贈ることができます。なので、相手がどんなものに関心を向けているか探ることは重要です。また、人はいいことをされたら、いいことを返そうという特徴もあります。そのため、相手が喜ぶプレゼントを贈ることで自分にも嬉しいプレゼントが返ってくるはずです。
では、みなさん楽しい年の瀬をお過ごしください。

11月の心理行動科学科
2021/11/30 >> 今月の心理行動科学科
11月20日(土)学校推薦型選抜の試験が行われました。体調不良の人もなく、志願者全員が小論文の課題と面接に臨みました。同じ日に社会人入学と編入学の試験も行われ、志願者が無事に試験を終えました。
11月23日(月)勤労感謝の日、仙台駅前アエル2階アトリウムにおいて「ココロサイコロ2021」が開催されました。
学科の1年生が3班に分かれ、半年間取り組んできた研究をパネル発表しました。
今回のテーマは「店舗利用行動の心理学」・「人助けの心理学 in 2021」・「リフレッシュする心を解き明かす」でした。
足を止めた方にパネルの説明をし、質問に答えていました。この経験がこれからの学びに活きていくことでしょう。
11月26日(金)には大原公務員ゼミナールの今村博之先生をお迎えし、公務員ガイダンスが行われました。
11月29日(月)には公認心理師、臨床発達心理士のOGに来ていただき、仕事についてお話をうかがいました。

ココロサイコロの様子


