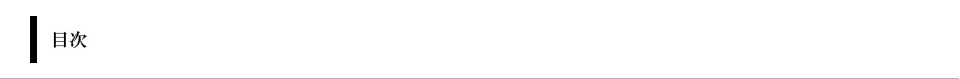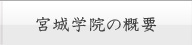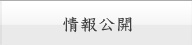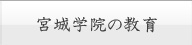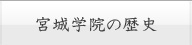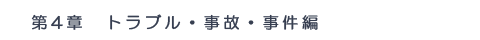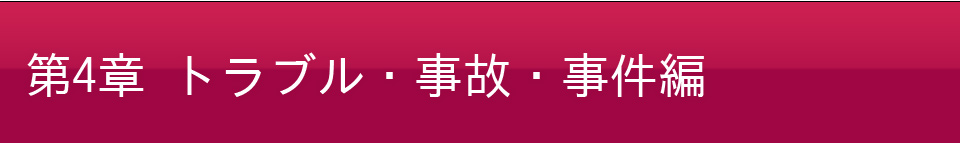
7. 心とからだ
(1) セクシュアル・ハラスメント/アカデミック・ハラスメント
セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは,相手がいやがるような「性的言動」によって,相手に屈辱感や不安感を与え,人格や尊厳を傷つけ,その結果,仕事や勉学をするうえで不利益を与えたり,仕事や勉学の環境を悪化させたりすることです。 セクハラは,働く権利や教育を受ける権利に関する侵害であり,男女雇用機会均等法で雇用者に対するセクハラ防止が義務付けられています。教育の場でも同様です。相手に対する直接的な言動だけでなく,卑猥(ひわい)な文書や写真を見せたり,公共性のある場所に掲示することなどによって不快感や屈辱感を与える場合も,セクハラに該当します。 セクハラは,異性間,教員-学生間に限らず,同性間,学生どうしの間で生じることもあります。 このほか,教職員からの勉学上の不適切な対応であるアカデミック・ハラスメント(アカハラ)も,キャンパス内で発生しうる人権侵害です。
<セクハラ … 2つのタイプ>
対価型・地位利用型
職務上の地位を利用し,または何らかの利益の代償あるいは対価として 性的要求が行われるもの。単位や成績,卒業,就職指導に大きな影響力をもっている教員が学生に対して行う,などがこのタイプ。
環境型
はっきりとした不利益は伴わなくても,それを繰り返すことによって,職務や勉学の円滑な遂行を妨げるなど,就業・勉学環境を悪化させる性的な言動のこと。学外サークルの先輩などによる性的な言動で,結果としてサークル活動に参加しにくくなる,などがこのタイプ。
セクハラを防止するには,セクハラを生み出してしまうような意識や環境(グレーゾーン(注))をどのようになくしていくかといった視点が必要です。
グレーゾーン(注) … 日常生活のなかで女性を「性的な関心の対象」や「劣った性」としてみな
したり,「女性の役割」を強いるような固定的な考え方など,セクハラには
至らなくとも放っておけばセクハラになりうるもの。
<もし,セクハラ/アカハラを受けたら…>
- 初期の段階で,「やめてください!」とはっきり意思表示をしましょう。
- 被害を受けた日時,場所,相手の具体的な言動,あなたの対応,その後の経過などを記録しておき
ましょう。
メモやメール,友だちに話すことも記録になります。 - セクハラ/アカハラを受けたら,泣き寝入りせず,行動に移しましょう。あなたの勇気ある行動が,
安全で快適なキャンパスライフを作ります。 - 一人で悩まず,学生相談室や信頼できる教職員,友だちに相談しましょう。学外にも相談機関があります。
主な相談先 … 学生相談室,特別支援室,保健センターなど
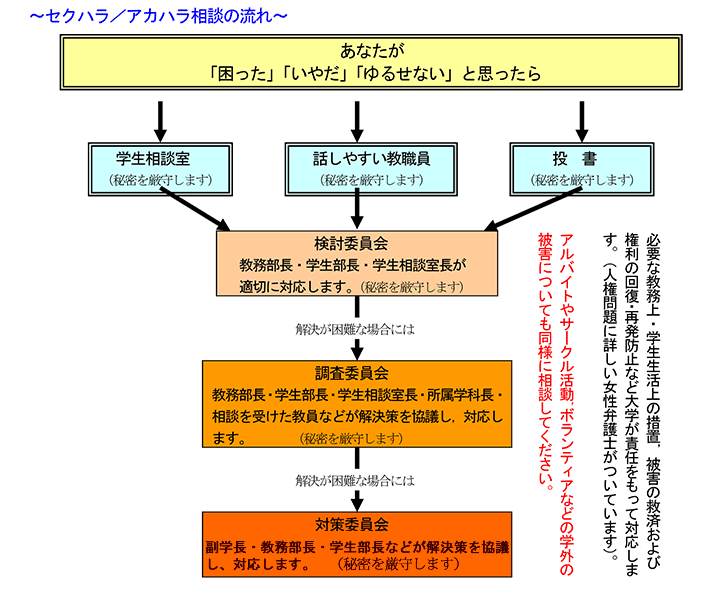
(2) デートDVから身を守る
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは,親密な関係にある一方(主として男性)が他方(主として女性)に対して,身体的・性的・精神的・経済的暴力を繰り返し,相手を支配することをいいます。
未婚の若い男女のあいだに起こるDVをデートDVといいます。
■「男性の乱暴や支配的な態度は,愛の証」と思っていませんか?
暴力は相手を支配するためのテクニックです。彼があなたを支配しようとするのは,あなたを大切に思っているからではなく,逆にあなたの気持ちなどどうでもいいと思っているからです。暴力は決して「愛情」を示す方法ではありません。
※暴力にはサイクルがあります。3つのステージを繰り返しながら,徐々に暴力の程度が過激さを増していきます。
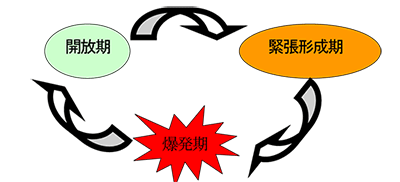
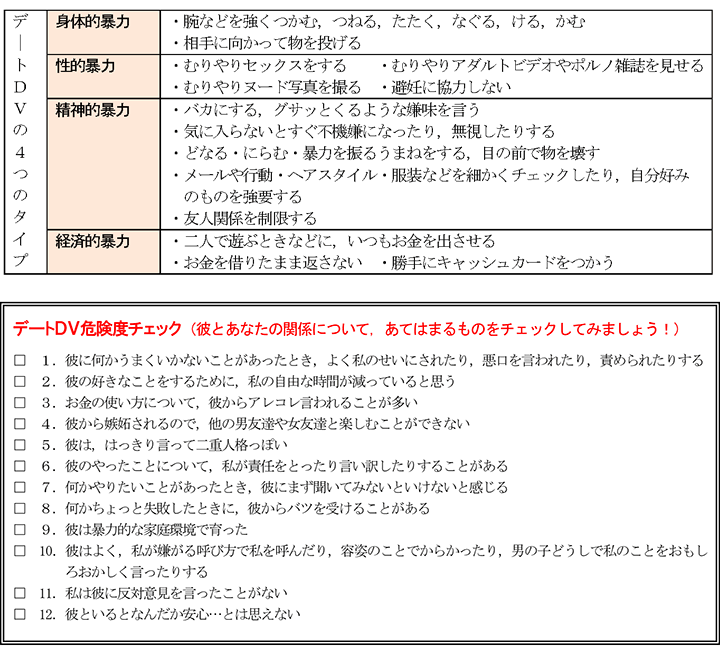
チェックの数はいくつになりましたか?
1~2 要注意。問題のあるところを放っておかずに,変えていけるか試してみましょう。
3~4 マジメにふたりの関係を見つめなおしたほうがいいですね。信頼できる大人に相談することをおすすめします。
5~6 ふたりの関係は,かなり壊れています。彼はかなりのDV男。あなたの安心と安全と元気がなくなる前に行動が必要です。
7~12 ふたりの間にはデートDVが起きています。専門機関に相談して。あなたの心と体にはいろんな変調が起きていませんか?
まずはあなたの安全を守ることを考えて!
(山口のりこ「デートDV」梨の木舎,」2003年より)
デートDVの被害を受けたら…
彼に「暴力は許せない」とはっきり伝えましょう。
たとえそのときには言えなかったとしても,また,彼が泣きながら謝ったので許してしまったとしても,
彼が冷静になったときに,毅然として,「暴力は許せない!」と言いましょう。
そうでないと,彼は暴力を容認されたと思い込んでしまいます。
怖くて何も言えなかったら/彼が暴力を繰り返したら
彼を好きになったのはなぜか?彼と一緒にいて心が休まるか?彼と何でも話しあえる関係か?…など 彼との関係を見つめなおしてみましょう。愛しあうとは,一方がいつも我慢を強いられているような関係ではないはず。我慢していても解決の道はありません。ひとりで悩まず,学生相談室や信頼できる人に相談してみましょう。
暴力がエスカレートしたら…
もし,彼の暴力がエスカレートして,あなたが恐怖や身の危険を感じるようになったり,けがを負ったりしたら,自分を守ることを考えましょう。
●逃げる
その場から逃げましょう。そして周囲の人に助けを求めましょう。
逃げることは勇気のいることですが,自分のためにできるとても大切な行動です。
●専門の相談機関に相談する
- 女性のための相談支援センター … DV被害に詳しい専門員が相談にのってくれます。
- 110番(警察)… 身体的暴力や脅迫,ストーカー行為をされたら警察の助けを求めましょう。
- 病院 …
けがをしている → 体調がおかしいときには病院へ行きましょう。
性的暴力を受けたときは → 妊娠の危険がなくても,STD(性感染症)の危険はあります。 産婦人科へ行きましょう。
●彼との関係を終える
暴力は加害者自身にしかなおせません。
あなたは「彼には私の助けが必要だ」と思うかもしれませんが,暴力は加害者自身が過ちを認め,
なおしたいという強い意思をもたない限りなおりません。それには,長い時間と専門家の助けが必要です。
別れるという選択は,デートDVから自分を守る確実な道です。
相談機関 → 宮城県女性相談センター:022-256-0965 /NPO法人ハーティ仙台:022-274-1885
エルソーラ仙台 →
女性相談:022-268-8302 / 女性への暴力相談:022-268-5145
(3) 薬物は怖い!
きっかけはちょっとした誘惑から…
みなさんの日常生活のあちこちに,薬物への誘惑がひそんでいます。薬物使用を始めるきっかけは,快感への追求,好奇心といったものがほとんどと思われていますが,それだけではありません。「やせられる」「自信がつく」「充実感がある」といった誘い言葉につい乗せられ,危険な薬物とは知らずに手をだしてしまうケースもあるのです。遊び友達・昔の同級生や職場の仲間など身近な人にすすめられ,いつのまにか薬物乱用に染まってしまう場合もあります。また,偶然の出会いも多く,とくに未成年者の場合,たまたま行った友人宅のパーティーでシンナーやマリファナと出会い,その後乱用をくりかえすといったケースがよくみられます。
乱用される危険のある薬物
×興奮作用 … 覚せい剤,コカイン,MDMAなど脳を刺激して興奮させる薬物
×幻覚作用 … 大麻,LSD,MDMA,マジックマッシュルーム,有機溶剤(シンナー,トルエン,接着剤など)など
実際にはないものが見えたり,ない音が聞こえたりする薬物
×抑制作用 … あへん系麻薬(ヘロイン,モルヒネなど),向精神薬(催眠薬,精神安定薬など)など脳を麻痺させて,
眠らせたり気分を鎮めたりする薬物
※危険ドラッグ(違法・脱法ドラッグ)
ハーブやお香などの形態で「合法」「法律に違反しない」などネットを中心に販売されている危険な薬物。麻薬や覚せい剤などと同様の危険性が指摘されている。
薬物を乱用すると
×急性中毒 … 薬物の作用により,生体に引き起こされる急性の影響(交通事故,暴力など反社会的行動,急性中毒死など)
×薬物依存 … 薬物を反復して使用しているうちに薬物の虜(とりこ)になり,自力では薬物をやめられない状態(薬物探索行動(注1),
退薬症状(注2),禁断症状など)
×精神の障害 … 薬物の直接的作用により引き起こされる脳の障害。幻覚・被害妄想などの精神病の症状や,意欲の減退などが現われる。
×身体の障害 … 薬物の直接的作用により引き起こされる全身の臓器に見られる障害
×後遺症状 … 薬物の使用をやめた後も長期にわたり残る症状(人格の変化,無気力・忍耐力の欠如などの社会不適応など)
薬物探索行動(注1) … うそをついたり,窃盗,恐喝,売春などあらゆる手段を使って薬物を手に入れようとする行動
退薬症状(注2)… 薬物を中断したときに現われる不眠・嘔吐・下痢などの苦痛を伴う心身の症
状。禁断症状は,
薬物を急激に中断したときに現われる類似の症状
薬物乱用の恐ろしさ
薬物を使用することは,単に使用者自身の精神や身体上の問題にとどまらず,家庭内暴力などによる家庭崩壊,さらには殺人・放火など悲惨な事件の原因にもなり,社会全体への問題と発展します。一度だけのつもりがいつのまにか中毒となり,一度しかない人生が取り返しのつかないものとなるのです。みなさんもこのような薬物乱用の恐ろしさを十分に理解し,日々の学生生活を健全にすごしてください。
どんなにすすめられても,薬物には手を出してはいけません。「ダメ。ゼッタイ。」
(4) 飲酒
クラブ・サークルなどでの新歓コンパ,イベントの打ち上げなど,大学生になると飲酒の機会が増えてきます。しかし,意外にも日本人の40パーセントがお酒に弱く,4パーセントがまったくお酒を飲めないといわれています。つまり,日本人の2人に1人はお酒に弱いのです。なおさら,お酒は適量を超えるとからだにさまざまな障害を与え,とくに短時間に大量のアルコールを摂取すると,血中アルコール濃度が急激に上昇し,場合によっては,呼吸困難など危険な状態を引き起こし,死に至ることもあります。次の注意点をよく読んで,自覚と責任をもって節度ある行動を心がけてください。
<注意事項>
●未成年者の飲酒は法律違反!
- 満20歳未満の者の飲酒は,「二十歳未満の者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」で禁止されており,飲酒をすすめた人も法律で罰せられます。
- 学年のまたがる飲酒の席では,前もって20歳未満かどうかを確認し,飲酒をしない,飲酒をさせないようにお互いが注意しましょう。
イッキ飲みを絶対しない・させない!
- イッキ飲みのように大量のアルコールを短時間に飲むと,急性アルコール中毒を引き起こすことになります。
急性アルコール中毒は,体内のアルコール濃度が高まって意識レベルが低下し,嘔吐,血圧低下,呼吸数低下などをきたし,
一気に「泥酔」「昏睡」の状態にまで進みます。ひどいときには死に至る自殺行為だといえます。 - 飲酒の席では,「イッキ飲みをしない」ことはもちろんですが,「イッキ飲みをさせない」ことも大切なルールです。
●飲酒運転は絶対しない!
- 飲酒運転は犯罪です。飲酒後は,自動車・バイクだけでなく,自転車の運転も絶対しないこと。
- 飲酒運転は,運転者はもちろんのこと,車両提供や酒類提供,同乗した者にも厳しい罰則が設けられています。
(5) 心とからだのトラブル
中高校生のみなさん
■スクールカウンセリング
みなさんの学校生活での困りごとや悩みに臨床心理士の資格のあるカウンセラーが相談に応じます。
生徒のみなさんだけでも,保護者の方だけでも相談することができます。申し込みは予約制です。
カウンセリング室:JSC305 電話022-279-1303
■保健室
保健室は,中・高生徒の健康診断,健康相談,保健調査,予防処置,救急処置,傷病者の休養など保健養護を行うために設けられています。
月~金 … 8:40~16:40 随
土 … 8:40~13:00 時
保健室:JSC214 電話022-279-1301
学生の皆さん
■学生相談室
皆さんが学生生活を送るうえで困っていること,不安に思っていることなど,何でも相談できる場所です。独りで思い悩んでしまったとき,どうぞ気軽に相談してください。相談室のスタッフがお話を聞き,一緒に考え,皆さんが学生生活を楽しく過ごせるようにお手伝いします。
■特別支援室
特別な支援の必要な学生のために,サポートを行っている場所です。学生生活や講義,レポート課題が難しい,友達との会話が難しいなど,どうしてよいか困ったときは,気軽に相談してください。問題を解決するためのアイディアや困りごとに合わせたトレーニングでお手伝いします。
【開室日時】
学生相談室は9:30~18:00(受け付けは17:15まで)
特別支援室は8:50~18:00(受け付けは17:15まで)
【場 所】 本館1階保健センター隣
【電 話】 022-277-6211(学生相談室)
022-277-6276(特別支援室)
【申し込み方法】
「学生相談室」あるいは「特別支援室」に直接申し込んでください。相談員不在の場合は,ドアに備え付けの申込用紙(または学生手帳P25・26)に記入して,ポストに入れてください。
【そ の 他】
長期休暇中の相談受付については,ホームページまたは掲示されている「学生相談・特別支援センターだより」で確認してください。
■保健センター
学生時代は,「自分の健康は自分が守る」という意識を自ら育み,将来に向けて,健康の保持増進のための生活習慣を身につける大切な時期です。保健センターは,皆さんの健康のために次のような支援をしています。
【定期健康診断】
定期健康診断は,学校教育法,学校保健安全法,感染症法に定められており,年1回,4月に実施され,全学生は必ず受けなければなりません。この健康診断を受けることによって自分の健康状態を知り,病気の発見と予防に役立てることができます。
【健康相談】
健康のことについて不安を感じ,個別に相談したい場合は,遠慮なく保健センターに相談してください。校医による相談も次のとおり保健センターで行っています。
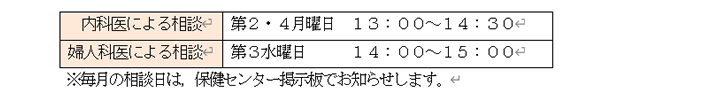
【応急手当】
学内での急病,けがなどに対して応急手当を行い,必要に応じて医療機関を紹介しています。静養室にはベッドが用意されています。具合が悪いときは我慢せず,早めに来室してください。市販薬については出していませんので,薬の必要な学生は,自分の体質に合ったものを各自用意してください。
(6) 熱中症
熱中症とは,暑い環境で行う運動などにより,体内の水分や塩分(ナトリウム)などのバランスが崩れ,体温の調節機能が働かなくなり起こるからだの障害です。原因としては気温が高いことだけでなく,湿度,風の強さ,日差しに影響され,体調にも左右されます。また,家の中でじっとしていても,室温や湿度が高いために熱中症になる場合があり,注意が必要です。
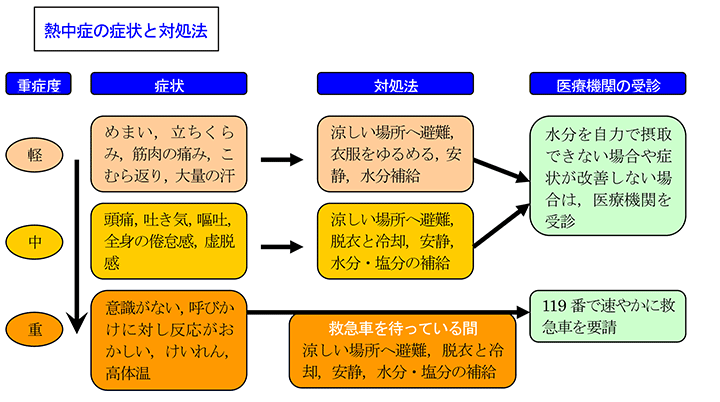
<熱中症予防のポイント>
●熱中症予防運動指針(日本スポーツ協会・2020より) ※気温は乾球温度
- 35℃以上 運動は原則中止
特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合は中止すべき。 - 31~35℃ 厳重警戒(激しい運動は中止)
熱中症の危険性が高いので,激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
10~20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人は運動を軽減または中止。 - 28~31℃ 警戒(積極的に休憩)
熱中症の危険が増すので,積極的に休憩をとり,適宜,水分・塩分を補給する。激しい運動では,30分おきくらいに休憩をとる。 - 24~28℃ 注意(積極的に水分補給)
熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに,運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 - 24℃以下 ほぽ安全(適宜水分補給)
通常は熱中症の危険は小さいが,適宜水分・塩分の補給は必要である。市民マラソンなどでは,この条件でも熱中症が発生するので注意。
●こまめに水分補給
- 汗には塩分も含まれているので,スポーツドリンクか自作の食塩水(水1ℓに食塩1~2gを溶かす)を補給します。
- 補給のコツは,のどの渇きを感じる前に少量をこまめに補給することです。
1回につきコップ半分の100 ml(子どもは50~100 ml)の補給を心がけましょう。
●涼しい服装で
- 暑いときには,体をしめつけないゆったりした軽装にして,素材も吸湿性や通気性のよいもの(麻,綿など),
色は熱吸収率が低いもの(白,パステルカラーなど)を選びましょう。 - 屋外で直射日光に当たる場合は,帽子や日傘など日よけ対策を忘れずに。