| 大内 典 OUCHI, Fumi |
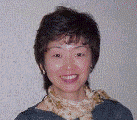
|
|||||
文化理論講義、基礎実習、音楽文化学講義
音楽学特講、生活音楽論講義
日本音楽史概論、音楽文化実習
卒業論文・卒業制作
|
|||||
学歴:
宮城学院女子大学音楽科卒業(ピアノ専攻)。
国立音楽大学大学院音楽研究科修了(音楽学専攻)。
研究領域:
民族音楽学、音楽文化学、日本の音文化
主要論文:
「『声』と『音』がつくる儀礼--修験道儀礼の音空間--」美学会編『美学』第160号、
「声と成仏---柴燈護摩における声の機能」庄野進・高野紀子編『音楽のテアトロン』勁草書房(1994)、
「あらがう音--羽黒修験の法華懺法--」『群馬県立女子大学紀要』第16号、
「神道行法における声の技法---『出羽三山神社錬成修行道場』の場合--」『群馬県立女子大学紀要』第17号、
「『ことば』と『ふし』の政治学--出羽三山の神仏分離と唱えごと」『群馬県立女子大学紀要』第19号。
最近の活動:
十数年におよぶ羽黒修験道の参与調査に基づき、2001年9月、ロンドン大学SOAS(The
School of Oriental and African Studies)の日本宗教研究センター主催のシンポジウム「神仏習合」において、"Kami-Buddha
Combination through sound.’’の論題で発表。2003年3月東京大学東洋文化研究所主催Mikkyo:
Ritual and Doctrine Conference/Workshopにおいて、“The Function of Sutra-Recitation
in Forming a Sound Community:The Goma Kito of Haguro Shugendo.”を発表。2004年4月より1年間、特別研修休暇でロンドンに滞在し、外国人研究者がもつオリジナルな視点を取り込みながら、修験道をはじめ日本独自の宗教文化を生んだ中世の音の文化に関する研究を進める予定。
|
|||||
プラス&情報:
幼い頃からピアノを習い、大学でもピアノを専攻。卒業後中学校の音楽教諭をするうちに、「“音楽”って何?」という疑問がむくむく。進学を思い立ち、大学院では民族音楽学の道へ。修士論文で扱った「法印神楽」という芸能が修験者(山伏)とゆかりの深いものだったのが縁で、修験道の音の文化を追いかけることになりました。自ら山伏になっての参与調査がいつのまにか十数年。修験道をより深く理解するために、密教僧の修行にも首をつっこみました。音、とくに声という人間の身体と最も密に結びついた表現媒体は、それぞれの文化の根源に深く関わるものだと思え、興味がつきません。家族と2匹の愛猫と、まっすぐでパワフルな学生たちの勢いを支えに、走り続ける日々です。
 音楽科トップページにもどる
音楽科トップページにもどる